私たちの研究室では、自由な雰囲気のもと、メンバーが各自のペースで研究活動を実施しています。
研究室で重視していることは、
- 常識にとらわれないこと
- 失敗を恐れずにチャレンジすること
- とにかく、全力を尽くすこと
です。
このような姿勢ができていれば、必ず研究成果はついてきます。
とはいえ、未知のことに挑戦しているわけですから、努力が研究成果として間違いなく表れるとは限りません。
たとえ、研究成果として実を結ばなかったとしても、苦労して得た経験や人脈というのは、その後の人生にかけがえのない宝になるはずです。
研究室では、挨拶と会話を重視します。これは、発想の瞬発力を鍛えます。
たとえば、廊下で誰かとすれ違うとします。このとき、あなたの頭の中では、いろんな考えが働きます。
最悪なのは、黙ってすれ違おうという考えです。
そこを頭を巡らせて、何か一言気の利いた言葉をかければ、そこであなたの印象もアップしますし、あなたの発想も鍛えられたことになります。
このようなことの繰り返しで、研究だけでなく、発表、発想力が鍛えられると思います。
ぜひ、このような研究生活を過ごしてみたいと思いませんか。




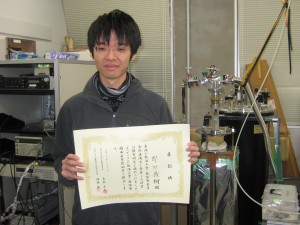

![IMG_2107[1]](http://sk.kuee.kyoto-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2014/11/IMG_21071-300x225.jpg)
![IMG_2108[1]](http://sk.kuee.kyoto-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/2014/11/IMG_21081-300x225.jpg)