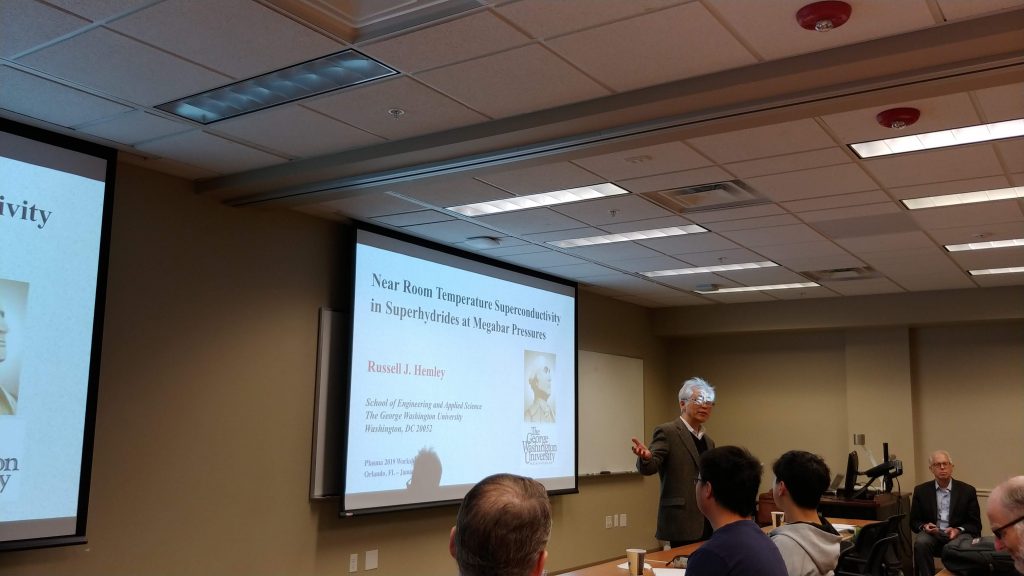高温超伝導体Bi2212単結晶から作成されたテラヘルツ放射デバイスについての論文がPhysical Review Applied誌から発表されました。本論文は、現M2の小林亮太、元修士課程院生の巴山顕が中心となって進めた実験の成果を産業技術総合研究所の辻本学博士と共にまとめたものです。
本論文では、放射テラヘルツ波の偏光測定結果について線形代数を用いた解析を行うことにより、同期する二つの素子からの放射電磁波の位相差が周波数に応じて変わっていくことを示しています。本論文で得られた成果をもとに系統的に調査を進めていくことにより、Beyond 5Gに求められる超高速通信のキャリア光源として有用なテラヘルツ電磁波を放射する超伝導デバイスが実現可能になります。